学ぶことで変わる、こころのバリアフリー
日本には約700万人の障害者が暮らしています。
杖や義足、車椅子などを使って生活する人たちのために、バリアフリーの重要性はますます高まっています。
1. 「こころのバリアフリー」の社会をめざして

「共生社会」とは、障害の有無にかかわらず、すべての人が尊重され、共に暮らす社会です。
現在、日本には車椅子利用者が200万人以上いると言われています。
たとえば、
- 困っている人に声をかけたいが、どうすればよいか分からない
- 手助けが逆に迷惑になるのではと不安になる
- 関わり方が分からないために何もできない
このような戸惑いは、関心がないわけではなく、「知らないから」生まれているのです。
2. 知ることで行動が変わる

多くの人は、学校や家庭で障害者と接する機会がなかったため、関わり方が分からないまま大人になります。
英語が話せない日本人が外国人に声をかけられると緊張してしまう──このような感覚に似ているかもしれません。
知らなければ行動できない。だからこそ、学ぶことが第一歩なのです。
3. 相手の立場を想像することの大切さ

障害のある方の中には、自分の状態を説明することが難しい方もいます。
一方、健常者も「どう関わればいいか分からない」と感じてしまいます。
こうした「お互いに知らないこと」が壁を生んでいます。
だからこそ、少しだけ想像力を働かせることが、バリアフリーへの第一歩になるのです。
4. 「障害者=かわいそう」という思い込み
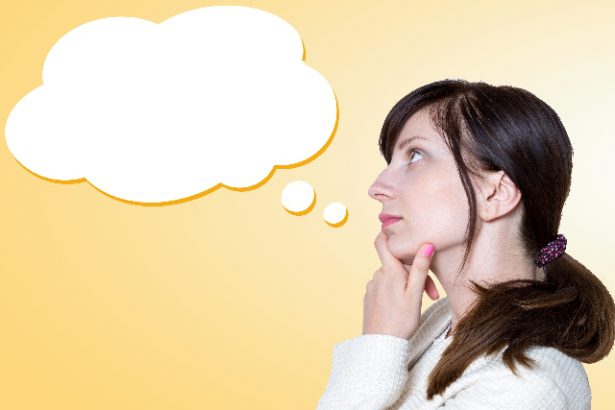
メディアでは「障害があるのに頑張っている」など、感動を呼ぶ演出が多く見られます。
しかし、これはオーストラリアの障害者活動家ステラ・ヤングさんが「感動ポルノ」と名付けて問題提起しました。
感動ポルノとは、障害者を感動の対象として利用する表現のこと。
「障害者なのに○○」という先入観を捨てて、一人の人間として接する社会が求められています。
5. 少数派の視点が社会を変える

世の中は右利き向けに設計された道具や仕組みであふれています。
同様に、障害者や高齢者が感じている“見えにくい不便さ”にも気づきにくいものです。
その「気づき」によって、社会は大きく変わります。
左利き用のはさみがヒット商品となったように、少数派の声が新たな価値を生むこともあるのです。
▼ YouTubeでも学べます
バリアフリーに関心をお持ちの方は、YouTubeチャンネル「バリアフリースタイルTV」でも情報を発信しています。





