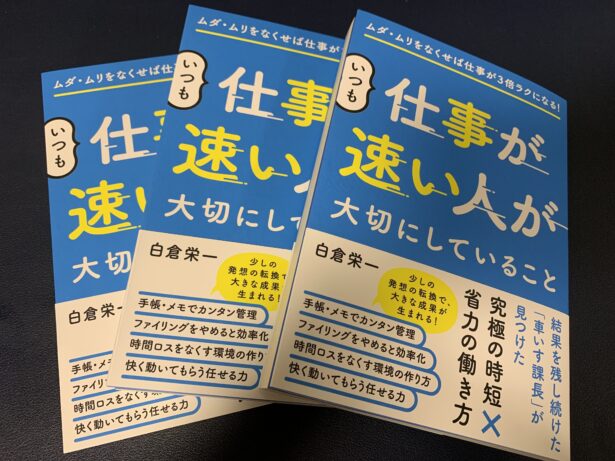「車椅子の人事総務課長が伝える『障害者雇用』のリアルと可能性」
バリアフリーアドバイザーの白倉栄一です。
私は1995年にイオンリテール㈱(旧:ジャスコ㈱)に入社し、22年間にわたりサラリーマン生活を送りました。
しかし、入社1年目の24歳の時、スクーターでのもらい事故により脊髄を損傷し、車椅子での生活を余儀なくされました。
懸命なリハビリを経て職場に復帰し、38歳のときには、会社初となる「車椅子の人事総務課長」に就任することができました。
熱意を込めて話している白倉栄一-615x345.jpg)
店舗スタッフの働きやすさとお客様へのサービス向上を実現し、2013年には顧客満足度全国1位の表彰を受けました。
バリアを乗り越えれば、障害があっても活躍できる環境は必ずつくれると実感しています。
私の経験をもとに、「障害者の働き方」をより多くの方に伝えたいという思いから、2024年5月にビジネス書『いつも仕事が速い人が大切にしていること』(KKロングセラーズ)を出版しました。
この書籍では、障害の有無にかかわらず、どのように成果を出し、自分らしく働くかという視点でアドバイスをまとめています。
これから就職やキャリアアップを目指す障害のある方々にとって、そして障害者雇用を検討している企業の方にとっても、気づきや学びのきっかけとなれば幸いです。
バリアを越える「仕組み」と「意識」を一緒に見直してみませんか?
1. 法定雇用率における障害者雇用達成企業は約半分

現在、障害者雇用促進法により、民間企業には従業員数の2.5%(2025年5月現在)の障害者雇用が義務付けられています。
これは、40人以上の企業であれば、少なくとも1人の障害者を雇用しなければならないということです。
しかし実際には、法定雇用率を達成している企業は約半数にとどまっています。
未達成企業には、不足人数1人につき月額5万円の納付金が課される仕組みです。
この背景には、「適切な業務がない」「職場の安全性が確保できない」「採用時に適性が分からない」など、企業側の不安があることが、厚生労働省の調査からも明らかになっています。
また、「通勤は可能か?」「ジャンパーへの着替えができるか?」といった形式的な条件ばかりが注目され、本質である「入社後に活躍できるか」という視点が置き去りになっているように思います。
雇用とは、単なる数字の達成ではなく、「活躍できる環境」を整えることが本質です。企業にとっても、それが人件費に見合った価値を生み出す人材育成へとつながります。
2. 活躍できるステージを見つけることが重要なポイント

障害者雇用が進む一方で、早期に退職してしまう方も少なくありません。
その理由の多くは、「賃金や労働条件への不満」「人間関係のストレス」「仕事とのミスマッチ」「会社の配慮不足」といったものです。
「障害者枠で入社したから昇給がない」「役職がつかない」といった声もよく耳にします。
能力があるのに「あなたは障害者だから…」と決めつけられ、チャンスを与えてもらえない現実は、本人にとって大きな挫折です。
そのため、最近では障害者枠ではなく、あえて一般枠で応募する方が増えています。
「自分の力でチャンスをつかみたい」という意思の表れです。
しかし、企業側がその想いに応えられていない場合も多く、せっかくの意欲が埋もれてしまっているのは非常にもったいないことです。
一部の方は、自分の力で評価される士業(公認会計士、税理士、社労士など)を目指す選択をしています。
能力が正当に評価される環境を、自ら切り拓いているのです。
企業側には、採用した人材の能力を最大限引き出す責任があります。活躍の場をつくることで、企業の競争力にもつながるのです。
3. 障害者の立場にたって考えることが職場の環境を変える

障害者を雇用する際は、「どんな配慮が必要か」を本人から直接聞くことが何よりも大切です。
聞かれなければ我慢してしまうというケースは少なくありません。
例えば、私が職場復帰した際には、通常の机の高さでは膝が当たりパソコン入力が困難でした。
そんなとき、当時の人事課長が私のためにパソコン用の机を準備してくれたのです。
その一言、「何か困っていることはありませんか?」が、仕事効率を劇的に改善するきっかけとなりました。
必要な配慮は、トイレだけではありません。通路・机・引き出し・病状への理解など、幅広いハード・ソフト面での調整が求められます。
これらを整えることで、障害者だけでなく、健常者にとっても働きやすい職場になります。
さらに、日常的なコミュニケーションも重要です。
安全衛生委員会などを活用し、職場の課題を定期的に共有する場を設けることも効果的です。
最後に大切なのは、相手の「できないこと」ではなく「できること」や「強み」に目を向ける意識です。
▼バリアフリーの取り組みを映像でも紹介中
YouTubeチャンネル「バリアフリースタイルTV」でも、現場のノウハウや事例を動画でわかりやすく紹介しています。ぜひご覧ください。

【社外秘】人事総務課長時代の顧客満足度調査1位獲得(店舗名隠す)-1-615x418.png)