「それって本当に“バリアフリー”?共生社会に必要な“意識の視点”」
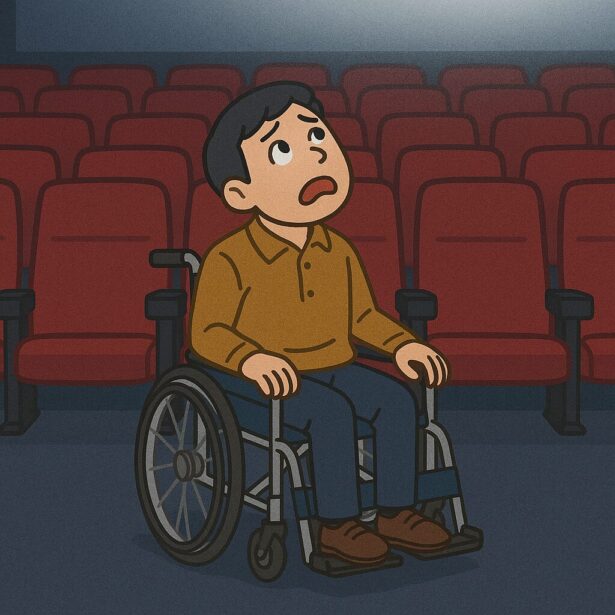
バリアフリーアドバイザーの白倉栄一です。
人は、どうしても「自分事」でないと、なかなか興味を持ちにくいものです。
たとえば、バリアフリーという言葉。
自分や家族・友人が困っていないと、関心を寄せる機会は少ないかもしれません。
実際に私がバリアフリーに関わる活動をしていても、
-
- 「いいことしてるね」
- 「でも今の自分には関係ないから…」
こんな反応をいただくことも少なくありません。
でも「共生社会」とは、自分と違う相手を“理解しようとする姿勢”が土台になります。
これは日常生活だけでなく、ビジネスにおいても非常に大切な考え方です。
自分とは関係ないと思ってしまう瞬間
ある日、車椅子利用者が映画館へ行きました。
でも多くの映画館で、車椅子用スペースは「最前列」のみにしか用意されていません。
さすがに、映画を最前列で見るのはかなり辛い体験です。首が痛くなるし、映像も見づらい。
そんな中、利用者が「もっと後ろで観たいな」と声を上げたとき、ある人はこう言いました。
「でも、バリアフリーにはなってるんでしょ?それ以上は贅沢じゃない?」
この言葉、あなたならどう感じるでしょうか?
少し視点を変えて考えてみましょう。
たとえば、もしあなたのスマホが壊れて、ガラケーしか使えなくなったとします。
そんなとき、誰かから「電話ができれば十分でしょ?」と言われたら、納得できますか?
おそらく、「それは違う」と感じるはずです。
つまり、自分が当事者になって初めて分かる“本当の不便さ”があるということ。
悪気のない言葉でも、相手を深く傷つけてしまう
映画館の話に戻しましょう。
車椅子席が「最前列にしかない」状況を、「十分配慮されている」と言えるでしょうか?
もちろん、施設の構造やコストの都合ですぐに改善できないこともあります。
でも、「もっと快適に楽しんでもらいたい」と考えること自体が、意識のバリアを減らす第一歩です。
「共に生きる社会」を目指すには、「自分には関係ない」と思ってしまう壁を乗り越えることが重要です。
“意識のバリア”に気づいたときが、行動のきっかけになる
今回ご紹介したのは、目に見えにくいけれど確かに存在する「意識のバリア」についてでした。
意識の持ち方一つで、誰かの行動を後押しすることもあれば、逆にブレーキをかけてしまうこともあります。
あなたの一言が、誰かの世界を変えるかもしれません。
関連する投稿
- 障害者と健常者との気軽なコミュニケーションをとれる共生社会へ
- 車椅子人口増加でも気軽に買い物・レストランへ行けること
- 車椅子に乗っている人って何が原因なの?①
- バリアフリーを自分事として捉えてみるための方法とは?⭐︎
- 東京パラリンピックのためには関心度を上げていく必要性
現在の記事: 「それって本当に“バリアフリー”?共生社会に必要な“意識の視点”」









