“お風呂が使えないバリアフリールーム”が生むミスマッチ──宿泊施設が見直すべき設計の視点
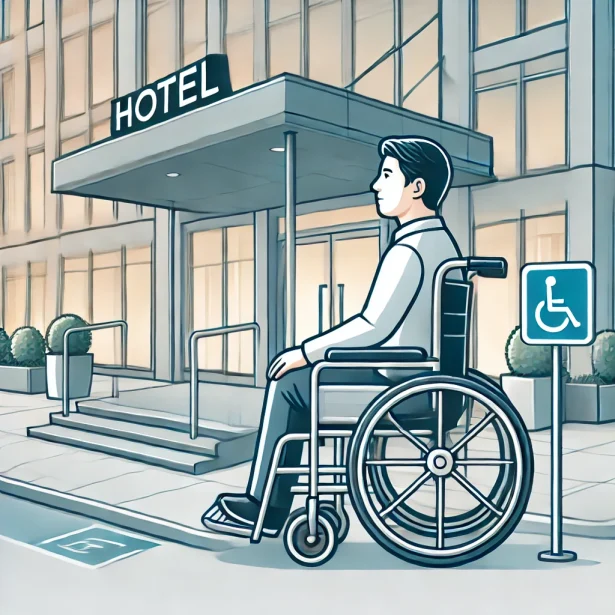
◆ バリアフリーを“知らない”からこそ、一歩踏み出すきっかけを
超高齢社会を迎える今、宿泊業界でも「バリアフリー対応」は大きなテーマとなっています。
ですが、単に“部屋を広くする”だけでは、使いやすい施設にはなりません。
今回は、車椅子ユーザーにとって最も重要な設備のひとつ「お風呂」について、具体的な課題と改善のヒントを紹介します。
◆ バリアフリールームでも“風呂が使えない”という現実
結論(Point):
バリアフリールームの多くが「お風呂に入れない」構造になっている──このミスマッチは見過ごせません。
理由(Reason):
旅行中に「ゆっくりお風呂に浸かりたい」と思うのは誰でも同じです。
しかし現実には、湯船に移乗しにくい構造や、補助設備の不備で“使えないお風呂”が多く存在します。
具体例(Example):
車椅子から湯船へ直接移るには、立位が困難な人には「中間の乗り移り台」が必須です。
ですが、これを備えている宿泊施設は極めて少数。
シャワーチェアがあっても固定されておらず、移乗時にぐらついて危険です。
結局“部屋が広いだけ”で、実際には使えないバリアフリールームと化してしまうのです。
◆ 「怖い」と思ったら、風呂には入らない
私自身も、ホテルの風呂を見て「これは危ない」と感じたら、入浴をあきらめます。
滑ったら大けが、手すりが不十分なら支えきれない──入浴にはリスクが伴います。
また、入浴中の姿勢や摩擦によって「褥瘡(床ずれ)」が発生する恐れもあります。
実際、私も旅先で皮膚がむけてしまい、血だらけになるアクシデントを経験しました。
お風呂は“癒しの空間”であると同時に、車椅子ユーザーにとっては“注意が必要な空間”でもあるのです。
◆ スノコや移乗台で、安全性と快適性は大きく向上
では、どうすればバリアフリーなお風呂になるのか? 解決策は3つあります。
- ① 浴室リフトの導入:天井レール式のリフトで安全に入浴できるが、設置コストと工事負担は大きい。
- ② スノコの活用:床面と高さを揃えれば、移乗の不安が大幅に減る。吸水・滑り止めマットとの併用が安全性アップ。
- ③ 移乗補助台の常備:例えば東横インでは、利用者と話し合いながら専用の移乗台を設置している。
設備に“完璧”を求めるのではなく、実際の使い方を想定して「これなら使える!」と思ってもらえる工夫が重要です。
◆ 今こそ“使える風呂”を備えた宿泊施設へ
これからは、車椅子ユーザーや高齢者が増えていく時代。
東京2020大会以降も、インバウンド・国内旅行需要は高齢層や障害者層が中心になります。
その中で、バリアフリー化を「費用がかかるから後回し」としていては大きなビジネスチャンスを逃してしまいます。
むしろ他の施設にはない“強み”を作るための投資として考えるべきです。
広いだけの部屋より、“ちゃんと使える風呂”がある宿泊施設こそ、これから選ばれる存在になるでしょう。
◆ まとめ|“使えるかどうか”の視点が鍵になる
バリアフリールームは「広さ」や「段差の有無」だけで判断されがちですが、
実際に利用する当事者にとって重要なのは「安全に使えるかどうか」です。
少しの配慮があれば、事故は防げ、安心は提供できます。
その発想が、宿泊施設の価値を高める未来への鍵になるのではないでしょうか。
関連する投稿
- 希少価値のバリアフリー店舗だからこそ造ることが狙い目になる⭐︎
- 店舗・施設のバリアフリー化が進むことによる大きなメリット
- 間違った駐車スペースの知識では車椅子のバリアフリーにならない
- 高齢化社会に伴う車椅子でも入れるトイレの設置が望ましい
- たった2段の段差が大きなバリアとして意味するものとは?
現在の記事: “お風呂が使えないバリアフリールーム”が生むミスマッチ──宿泊施設が見直すべき設計の視点









