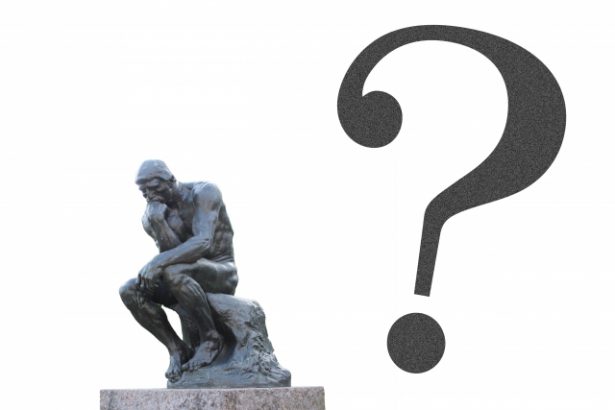車椅子ユーザーが困る身障者用駐車スペースの“カラーコーン問題”とは?

車椅子利用者が直面する意外な“障壁”とは?
身障者用駐車スペースの真ん中にカラーコーンが置かれていることがあります。
これは意外と知られていませんが、車椅子利用者が1人で来店した際、自力でカラーコーンをどかすことができないため、駐車場の係員にお願いしないと駐車できない状態になってしまうのです。
「そこまでしなくても…」と思うかもしれませんが、無断駐車を防ぐための対策として、多くの施設でカラーコーンが置かれています。
しかし問題は、その運用が徹底されていないことにあります。
車椅子利用者が「カラーコーンを動かしていただけませんか?」とお願いしても、すぐに対応してもらえなかったり、「自分で動かして」と言われてしまうケースも少なくありません。
こうした事例が多いため、商業施設などを運営する側はぜひ把握しておくべきポイントです。
インターホンでのやりとりに表れる“温度差”
以下は、実際によくあるやりとりの一例です。
- (係員)「どうされましたか?」
- (車椅子利用者)「車椅子でとめられる駐車場はありますか?」
- (係員)「えっ、なんですか?」
- (車椅子利用者)「車椅子でとめられる駐車場はありますか?」
- (係員)「○○階にあります」
- (車椅子利用者)「カラーコーンがありますか?」
- (係員)「あります」
- (車椅子利用者)「動かしていただけますか?」
- (係員)「ご自身で動かしてください」
- (車椅子利用者)「1人なので動かせません」
- (係員)「えっ?」
- (車椅子利用者)「止められないのですが…」
- (係員)「わかりました」
このようなやりとりが全国各地で繰り返されているのです。
地方では“バリアフリーの理解不足”が浮き彫りに
地方の商業施設では、係員に「身障者用駐車場はありますか?」と聞いたところ、「あっちにあるから〜」という曖昧な返答だけで、実際には1台分も見当たらないというケースも多くあります。
結果として、施設を利用できずに帰るしかないという悲しい事例もあるのです。
私が日本一周をしていたとき、九州の某百貨店で45分も並んだ末に、身障者用スペースがない場所へ案内され、断念したこともありました。
都心では配慮されていても、地方ではバリアフリーの知識そのものが行き届いていないことも少なくありません。
そのため、説明しても「聞く耳を持たない」「シャットアウトされる」といった心ない対応をされることもあります。
まずは“傾聴する姿勢”を持つことが第一歩
バリアフリーの基礎知識を持つことも大切ですが、困っている人の声にきちんと耳を傾ける“傾聴の姿勢”が何より重要です。
そのうえで、きちんと確認・対応することで、お客様からの信頼にもつながり、施設全体の評価も向上していきます。
せっかく接客マニュアルを整えても、最初に接する駐車場係員の対応が悪ければ、すべてが台無しになってしまいます。
だからこそ、駐車場係員こそ“施設の顔”としての教育が欠かせないのです。
関連する投稿
- 店舗のバリアフリーへの意識度が分かってしまうポイントとは?⭐︎
- バリアフリーの店舗かどうか一瞬で判断されるポイント
- 店舗の「バリアフリー」という表記だけでは分からない理由
- 車椅子でも利用しやすいショッピングモールをさらに活用できるポイント
- 企業間のコラボがあればバリアフリーの利便性は加速する
現在の記事: 車椅子ユーザーが困る身障者用駐車スペースの“カラーコーン問題”とは?