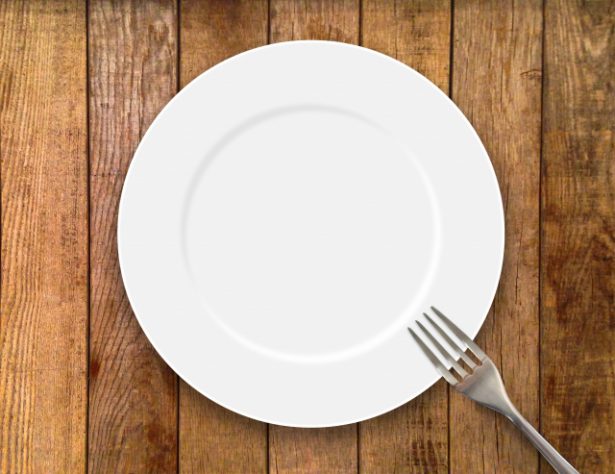「高い受付カウンター」が生む見えないバリア 〜車椅子ユーザーや低身長の方への気づきと配慮〜

バリアフリーアドバイザーの白倉栄一です。
最近はカフェスタイルのお店が多くなっており、受付カウンターの高さが100〜120cmほどのデザインが主流になってきました。
しかし、車椅子利用者の目線ではその高さのカウンターはちょうど同じか、やや上になり、メニューが見づらくなってしまうことがあります。
受付カウンターが高いと気軽に購入できない人がいる
車椅子利用者に限らず、身長の低い方や高齢者も高い受付カウンターには圧迫感を感じやすく、気軽に利用しづらい雰囲気になりがちです。
ちょっとコーヒーを飲みたいと思っていても、「どうしようかな…」と迷い、その結果「やっぱりやめよう」と思ってしまうことも少なくありません。
だからこそ、お店側の「さりげない一言」が大きな差を生みます。
お客さまがメニューを見て戸惑っているような様子があれば、「お探しのものがあればお声かけください」「メニューご案内しますよ」といった一言を添えるだけで、安心感が生まれます。
人は「迷っているとき」に背中をそっと押してもらえることで、一歩を踏み出しやすくなります。
たとえ利用されなかったとしても、丁寧な声かけが印象に残り、次の来店や口コミにつながることもあるでしょう。
接客対応は臨機応変にできるテクニックを育成する
受付カウンターを物理的に低くできない場合でも、「人の工夫」で補える部分はたくさんあります。
たとえば車椅子のお客さまが来店した際、従来通りカウンターの中から「いらっしゃいませ、何になさいますか?」と声をかけてしまうと、顔が見えず、威圧感さえ感じさせてしまいます。
こうしたときには、カウンターを離れてお客さまの目線まで近づいてご案内したり、メニューを手渡ししたりすることで、ずいぶん印象が変わります。
また、「セルフサービスですので、お水はご自身でお取りください」という一言も、場合によっては配慮に欠けた印象を与えてしまいます。
対応がマニュアルに偏っていると、柔軟さに欠ける接客になってしまいます。
価値観が違う相手にはことばで発しないと伝わらない
経験豊富な接客スタッフであっても、「自分なら分かるから相手も分かるだろう」という思い込みをしてしまいがちです。
しかし価値観が違う相手にとっては、説明や言葉がないと伝わりません。
部下やスタッフへの指導においても、「なぜその対応が必要なのか」をきちんと言葉にし、模範を示していくことが大切です。
チームで「どうしたら誰もが安心して利用できるか?」を考え実践することで、誰にとっても居心地の良い空間が生まれます。
まずは一歩。
お店側が気づき、声をかけ、行動することから、バリアのない接客は始まります。
関連する投稿
- ファミレスこそがバリアフリーの有無が伝わりにくい理由とは?
- 障害の部位・レベルに応じたバリアフリーを伝えることの大切さ
- 障害者も喜ぶお店づくり|設備設置後に必ずやるべき情報公開とは
- 「車椅子ユーザーが本当に使えるトイレとは?店舗が押さえるべきバリアフリーポイント」
- 予約の不便さが集客機会を失う|バリアフリー対応は“見える化”と“簡単化”がカギ
現在の記事: 「高い受付カウンター」が生む見えないバリア 〜車椅子ユーザーや低身長の方への気づきと配慮〜